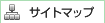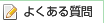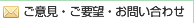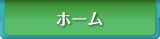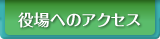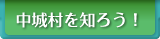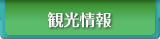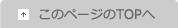農政係
掲載記事一覧:ご覧になりたい項目をクリックすると、その記事へ移動します。
- 中城村農業振興ビジョン【基本構想・基本計画】
- 農業振興地域とは
- 農用地区域の確認について
- 中城村 あたいぐぁ〜朝市について
- 島にんじんについて
- 島にんじんレシピについて
- 火入れを行うには村の許可が必要です!!
- 「人・農地プラン」から「地域計画」へ
- 中城村実質化された人・農地プランの公表について
- 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)の改正について
- 農地の利用権設定手続きについて
- 森林環境譲与税の使途公表について
- 中城村森林整備計画について
- 中城村農業用水対策施設設置補助金交付制度のお知らせ
- 飼養届の提出について
- 中城村鳥獣被害防止計画について
中城村農業振興ビジョン【基本構想・基本計画】
令和2年度から令和11年度までの10年間を計画期間として「中城村農業振興ビジョン」を策定しました。
今後、中城村農業の目指す方向として『持続的で発展的な夢ある農業』を基本理念とし、村役場、農業関連団体、生産農家及び村民の皆様との連携・協働により農業振興を推進します。
・中城村農業振興ビジョン
・中城村農業振興ビジョン【概要版】
農業振興地域とは
中城村では「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき「中城農業振興地域整備計画書」を策定し、農業振興地域内において農用地区域(農振農用地)を指定しています。
農用地区域とは、農業の健全な発展を図るため、土地の自然条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、土地の農業上の利用、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域の保全及び形成すること、並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関することを目的として定められた地域です。
そのため、農用地区域は土地利用が制限されており、農業の目的以外には使用できませんのでご注意下さい。
※上記の整備計画及び土地利用計画図は、農用地区域の内外を証明するものではありません。
詳細(筆ごと)の確認は、産業振興課窓口又はFAXでの確認をお願い致します。
中城農業振興地域整備計画変更
中城農業振興地域整備計画の変更は、年に2回受付を行っている一部見直しと概ね10年に1度行っている中城村全体の見直しがあります。
一部見直しにおいて農用地区域から除外の対象となるのは農家住宅、農家の分家住宅、墓地、公用・公共用施設等があり、その他の目的による除外は全体の見直しで検討することになります。
農振農用地区域の一部変更(一部農振除外)について
農振農用地区域からの除外を希望する方は、以下の申請が必要になります。なお、申請にあたっては次の要件を満たす必要があります。
除外申請要件
1 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2 農用地の集団化、作業の効率化及びその他の農業上効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
4 除外する面積が必要最小限であること
5 農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれるものであること
6 除外申請用途が次にいずれかであること
(1)農家住宅(2)農家の分家住宅(3)農林水産物用施設(4)個人墓(5)公益の高い施設(病院、保健福祉施設等)
申請受付期間
上期: 当該年度4月1日〜5月31日
下期: 当該年度10月1日〜11月30日
※ただし、受付期間終了日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日までの受付です。
申請に関するお問い合わせ先:産業振興課 895−2163
申請書類
- 農用地利用計画変更申請書
- 申請地付近を示す見取り図
- 申請地の登記事項証明書(全部事項)
- 申請地の公図の写し
- 施設の配置図(平面図・配置図)
- 資産証明書(土地所有者及び利用者の全資産)
- 申請地付近の写真
- 土地利用同意書
- 農用地利用計画変更申請書類提出書類
農用地区域の確認について
農用地区域の確認は、産業振興課の窓口において確認することができます。
電話での確認は行っていませんが、FAXによる確認は可能です。
FAXによる確認の際は、下記「農振農用地確認票」をご利用ください。
・農振農用地確認票(FAX用)Word
農用地区域内の農地の用途区分変更(軽微変更)について
用途区分変更(軽微変更)とは
農用地区域内の農地(田、畑等)を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合は、農振除外は不要ですが、
「用途区分変更(軽微変更)」の手続きが必要となります。
農業用施設とは、畜舎、堆肥舎、温室、農産物貯蔵施設、農産物集出荷施設、農機具格納庫等をいいます。
また、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更にも軽微変更手続きが必要です。
用途区分変更(軽微変更)を行っても、農振農用地であることに変わりありませんが、
農地法で定義する農地(耕作の目的に供される土地)ではなくなるため、農地転用は必要となります。
また、用途区分を変更する面積によって開発許可申請等の手続きが必要となりますので、
詳しくは産業振興課窓口へご確認下さい。
用途区分変更(軽微変更)の要件
・申出する面積が計画する施設からみて適当で、1haを超えないこと
・既存施設からみて過大なものでないこと
・他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
・農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許可等の見込みがあること
用途区分変更(軽微変更)の手続きについて
【受付期間】
随時、産業振興課窓口にて受付しています。
【提出資料】
1.農業振興地域整備計画の一部変更(軽微変更)申出書
2.添付資料
(1)変更地付近を示す見取り図(案内図)
(2)変更地の登記簿謄本
(3)変更地の公図の写し
(4)事業計画書及び施設配置図(農業用施設の場合)
(5)変更地付近の全体の写真
(6)借地の場合は契約書の写し
【様式】
・農業振興地域整備計画の一部変更(軽微変更)申出書(様式)
・(記入例)農業振興地域整備計画の一部変更(軽微変更)申出書(農業用倉庫)
・(記入例)農業振興地域整備計画の一部変更(軽微変更)申出書(分筆)
中城村 あたいぐぁ〜朝市について
中城村のとれたて野菜や果物、草花の苗、海産物等を販売しています!!
※海産物につきましては、前日の天候等により出品が出来ない事がありますのでご了承下さい。
出店者は随時募集しています!
希望者は下記、実行委員会事務局までご連絡ください!
☆開催のお知らせ☆
【日時】 毎月第2・第4日曜日 午前8時30分〜11時
【場所】 中城村役場 新庁舎駐車場
【お問い合わせ】
朝市実行委員会
会長 伊佐 盛好 TEL 090-4352-8423
事務局 金城 章 TEL 090-3794-4133
※売切次第終了、出店者は相対販売です。
島にんじんについて
島にんじんレシピについて
中城村の特産品である島にんじんのレシピです!ぜひお試しください!
レシピは随時更新していきます!

★クリーミーな島人参スープ ★ピリ辛ウマ島にんじんのナムル ★ほんのり甘い島にんじんサラダ
★栄養満点チムシンジ汁 ★爽やかツバキ漬け ★島にんじんのゴマよごし
★しっとりふわふわ島にんじんロールケーキ(中城村 プチ・スウィート考案)
★とろける島にんじんプリン (中城村 プチ・スウィート考案)
その他にも下記のバナーにて沢山のレシピを紹介してます。
↓
火入れを行うには村の許可が必要です!!
森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある原野、畑、その他の土地において火入れをする場合は、村の許可が必要です。(森林法第21条及び中城村火入れに関する条例)
◆許可の条件
火入れの目的及び条件につきましては、下記のとおりです。
造林のための地ごしらえ
開墾準備
害虫駆除
焼畑
(1)〜(4)のいずれかに該当し、現況や防火設備、気象状況から延焼の恐れがない場合
◆申請方法
火入れの10日前までに「火入許可申請書」を産業振興課に提出してください。
申請書には、火入れする土地の現況・期間・目的・方法・防火の体制・責任者等を記入し、見取図や他人の土地である場合は、所有者等の承諾書を添えてください。
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
これまで、地域での話合いにより「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、農用経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」は「地域計画」として法定化されました。
地域計画では、農業者や地域の皆様の話合いにより、「地域農業の将来の在り方」を示すとともに、将来の農地利用を明確化した「目標地図」を新たに作成します。
村では、法令に基づき、令和7年3月末までに、地域・農業者・関係機関との話合いを経て、地域計画を策定し公表することとしています。
地域計画とは
各地域での話合いをもとに、高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加など、地域農業が抱える「人と農地の問題」を解決する「未来の設計図」(人・農地プラン)と目標地図を合わせたものが「地域計画」です。
地域計画の主な作成手順は以下のようになります。
1.各対象地区においてアンケート調査を実施します。
2.アンケート調査結果をもとに、農地の現況地図を作成します。
3.現況地図をもとに、農業者や地域住民、関係機関と地域農業の将来の在り方について話合いを行います。
4.村は、話合いの結果を取りまとめ公表します。
5.地域での話合いをもとに、地域計画と目標地図の素案を作成します。
6.作成した素案の説明会を開催し、農業者や地域住民、関係機関の意見を聴取します。
7.村は、上記の意見を踏まえ地域計画の案を作成し、縦覧を行います。
8.村は、縦覧後に地域計画の策定について公告を行います。
地域計画にむけたアンケート調査について
1.アンケート調査の目的
地域座談会の開催にあたり、農地の現況を把握する現況地図の作成のため、農地地権者を対象にアンケート調査を実施しました。
2.調査期間
令和5年12月末〜令和6年3月末
3.調査対象
(1)対象農地:1216筆
村内土地改良区(当間・和宇慶・和宇慶川崩原土地改良区)及び上地区(登又・新垣・北上原)の農地の内、660?(200坪)以上の農地を対象とした。
※660?以上の根拠については、担い手農家が集約する際に要望する農地の最小面積
(2)アンケート対象者:910名
アンケート対象者として、2023年10月時点の地籍情報により、住所地番不備を除く、現況地目「畑」 の土地所有者(登記名義人)である個人や民間企業を対象とした。
※官公庁、電力・ガス事業者等を含む大企業のほか、自治区名義等は対象外
アンケート調査の結果については、☞『アンケート調査集計分析結果』をご確認下さい。
農業みらい地域座談会キックオフセミナーの開催について
中城村では、10年後の農業について考える「農業みらい地域座談会」の開催を計画しており、地域座談会開催の前に地域住民の皆様に、本村の農業の現状や座談会で話合う内容について説明するキックオフセミナーを令和6年4月25日(木)に中城村吉の浦会館にて開催しました。
キックオフセミナーでは、村内の担い手農家や農地地権者また関係機関など約130名にご参加頂き、本村の農業の現状、地域座談会の目的や座談会の進め方また目標について説明がありました。
今後、村では、各地区において計画策定にむけた座談会を実施していく予定です。
 |
 |
| 開会あいさつ(中城村長) | 会場の様子 |
 |
 |
| 産業振興課による村内農業の現状説明 | 講師(澤畑氏)講演 |
農業みらい地域座談会について
中城村では、村内の農業者や地域住民等を対象に、10年後の農業の将来像について考える「農業みらい地域座談会」を開催いたします。
座談会では、ファシリテーターとして全国各地でご活躍されている澤畑佳夫氏(全国農業会議所専門相談員)を迎え話合いを行います。
中城村の農業の将来について地域住民の皆様と考える大変重要な座談会となりますので、地域住民皆様のご参加宜しくお願い致します。
詳細につきましては、☞『農業みらい地域座談会』をご覧ください。
第1回農業みらい地域座談会の開催について
中城村では、地域計画の作成にむけ10年後の農業について考える「第1回農業みらい地域座談会」を開催いたしました。
第1回目の座談会では、各地区における農業の将来像について参加された方全員の思いや考えを聴き合うことからスタートし、下記の様な目標(理想像)が出されました。
・理想像順位表
第2回目の座談会では、各地気における目標(理想像)の絞り込み及び具体的な取組について話合いを行います。
第2回目座談会の詳細につきましては、☞『第2回農業みらい地域座談会の開催について』をご確認下さい。
【第1回座談会の様子】
 |
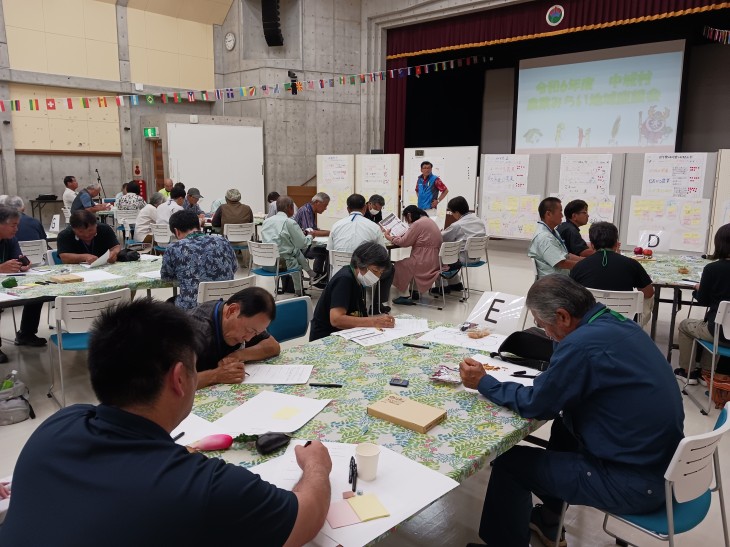 |
| 和宇慶土地改良区Aグループ | 和宇慶土地改良区Bグループ |
 |
 |
| 当間土地改良区Aグループ | 当間土地改良区Bグループ |
 |
|
| 上地区グループ |
中城村実質化された人・農地プランの公表について
「人・農地プラン」とは、農業者が話し合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)、当該地域における農業の将来のあり方などを明確化し、市町村により公表されるものです。
農業者の高齢化や担い手不足など農業を取り巻く課題が山積する中、中城村では令和2年度に別添(工程表)のとおりプラン作成を進め、令和3年度に実質化しましたので公表します。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)の改正について
農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月付)に伴い、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)を変更しましたので、農業経営基盤強化促進法第6条第6項及び施行規則第5条に基づき公表します。
・農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和5年9月改正)
農地の利用権設定手続きについて
利用権設定とは
利用権設定とは、農地法第3条許可とは別に、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地の利用権を設定する手続きです。利用権は、村が農業委員会の決定を経て農地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法上の許可は必要ありません。)
利用権設定の特徴(メリット)
【出し手】
利用権設定期間終了後は、自動的に貸借関係が終了し、農地が戻らないなどの不安がなく、安心して農地を貸すことができます。(※農地法第3条許可と違い、自動更新とはなりません。)
【受け手】
賃貸期間が明瞭なため安定的な営農計画が立てられます。
農地法第3条許可と違い、経営面積の下限面積要件(中城村では20アール=2,000?≒約606坪)を満たしていなくても借り受け可能です。
申請者(出し手及び受け手)の要件
【出し手】
農地の所有権を有している方(所有者が死亡している場合は相続人)
※所有権を有している方や相続人が複数いる場合は、利用権を持っているすべての人の同意が必要です。ただし、賃貸期間が5年以内の場合は、過半数の同意でも可能です。
(人数ではなく、持ち分での過半数が必要です。なお、トラブル回避のため、原則全員の同意が得られている方が望ましい。)
【受け手】
・農地の全てを利用して効率的に耕作又は養畜の事業を行う方
・必要な農作業に常時従事する方
・農作業に必要な農機具を有している方
・地域の他の農業者との適正な役割分担のもとに継続的かつ安定的に農業経営を行う方
その他
・賃借期間については、出し手及び受け手の話合いで決めて下さい。
・賃借、納付期日及び納付方法については、出し手及び受け手の話合いで決めて下さい。なお、無償も可能です。
・賃貸期間の途中でも、お互いの合意があれば解約することが可能です。
利用権の設定を行うための手続き
出し手及び受け手で話し合い、必要書類を整え村役場産業振興課窓口へ提出してください。
なお、書類提出の締切は毎月10日(土日祝日の場合は直後の開庁日)となっており、賃借の始期は、早くとも翌月1日以降となります。
※締切日以降に提出されたものについては、翌月の処理となり、賃借の始期は早くとも翌々月の1日以降となります。
必要書類
1.利用権設定等申出書
2.各筆明細及び共通事項
3.利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等
4.利用権設定に関する同意書(共有名義) ※所有権を有している方や相続人が複数いる場合
5.申出地に係る登記簿謄本・公図 ※法務局で発行
6.借り手が他市町村在住者である場合には、耕作証明書 ※在住市町村の農業委員会等で発行
7.貸し手及び借り手に他市町村在住者がいる場合は、その者の住民票謄本
8.開発を伴う場合は、開発事業計画書(添付書類含む)
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税とは
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税の使途については、適正な使途に用いられることが担保されるよう、インターネットの利用等により使途を公表することとなっています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、中城村における使途について以下のとおり公表します。
中城村森林整備計画について
地域の目指すべき森林資源の姿
森林整備に当たっては、森林の有する各機能の充実と機能間の調整を図り、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、重視すべき機能に応じた整備を行う観点から、特に発揮することを期待されている機能を有する森林を、7つの機能に区分し、機能に沿って育成単層林施業、育成複層林施業、天然林施業を計画的に実施し、望ましい森林資源の姿に誘導するよう努める。
中城村農業用水対策施設設置補助金交付制度のお知らせ
R5農業用水施設(井戸)設置補助金について
中城村では、農業用水対策施設(井戸)を設置する際に、最大10万円の補助金が受けられます。
今年に農業用水対策施設(井戸)の設置を考えている農業者の皆様はぜひ中城村役場産業振興課までご相談ください。
受付締切期限:令和5年12月28日(木)
※交付には一定の要件を満たす必要があります。
※申請が受理された補助金額が予算額を上回った場合、受付期間中でも申請受付を終了いたします。
中城村農業用水対策施設設置補助金について.pdf
申請書様式.pdf
(土地借用者のみ)農業用水対策施設施行承諾書
連絡先
産業振興課 TEL:098-895-2163
担当 産業振興課 護得久(内線234)
飼養届の提出について
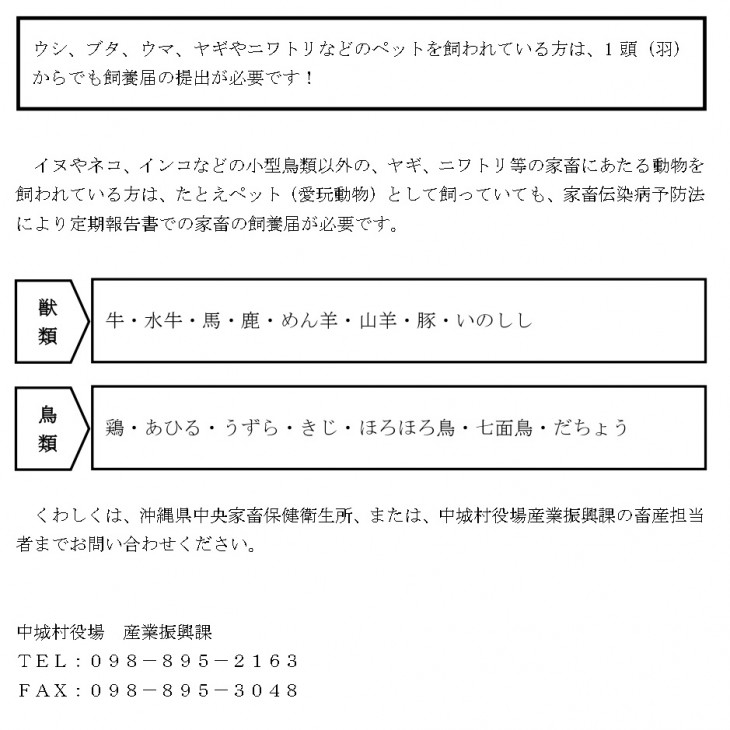
中城村鳥獣被害防止計画について
中城村鳥獣被害防止計画
中城村鳥獣被害防止計画を策定しましたので、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律第4条第9項の規定により公表します。
お問い合わせ先
中城村役場産業振興課
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048
電子メールによるお問い合わせ