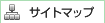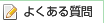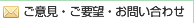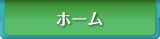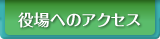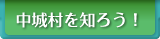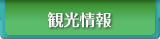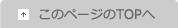こども課
掲載記事一覧:ご覧になりたい項目をクリックすると、その記事へ移動します。
| 令和5年度(2023年) 認可保育園等の申込みの案内について※他ページへ移動します |
| 幼児教育・保育の無償化について※他ページへ移動します |
| (吉の浦こども園)苦情処理の公開 |
| うえむら病院 病児保育事業の利用について |
| 吉の浦保育所に遊びにきませんか |
子育て支援係
児童手当制度について
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
改正1:現況届の提出が原則不要となりました
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が本村と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設(里親含む)等の受給者の方
- その他中城村から提出の案内があった方
※該当する方へ6月初旬に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。
期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
上記1から4に該当する方で、現況届の案内が届かない方はこども課までお問い合わせください。
改正2:特例給付の支給に係わる所得上限額の新設
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6〜9月分)より、特例給付の支給に係る所得上限が設けられます。
児童を養育している方(主たる生計維持者)の所得により、支給は以下のとおりとなります。
児童手当支給額
- 所得が表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15,000 円または10,000円)を支給
- 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000 円)を支給
- 【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
児童手当所得制限限度額
| (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
| 扶養親族 の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
| 0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
| 1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
| 2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
| 3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
| 4人 | 774.0 | 1002.1 | 1010.0 | 1238.0 |
| 5人 | 812.0 | 1042.1 | 1048.0 | 1276.0 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
注意事項
児童手当は、児童を養育する父母等のうち、原則所得の高い方が受給者となります。
現況届(現況届提出省略対象者含む)の審査の結果、受給者変更が必要な場合は、以下の書類をご提出していただきます。
- これまで受給者であった方→児童手当支給事由消滅届
- 新たに受給者となる方→児童手当認定請求書
※受給者変更が必要な方には、電話にて連絡、または案内文を送付します。
消滅(却下)後の取扱いについて
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることが出来ません。
認定請求書が必要なケース
※所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった場合。
※所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった場合。
(補足)公務員について
公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。したがって以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。
- 公務員になったとき
- 退職等により、公務員でなくなったとき
- 現在公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき
よくある質問と回答
Q1:現況届が届きません
A1:これまで、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて提出が不要となりました。提出を求める人へ、6月に本村から現況届を送付しますので、期日までに提出ください。
Q2:今回の改正は手当の何月分から変わりますか
A2:令和4年6月分(10月支給)の児童手当等から変わります。児童手当は該当月に応じて年3回支給しています。
- 2月・3月・4月・5月分:6月支給
- 6月・7月・8月・9月分:10月支給
- 10月・11月・12月・1月分:2月支給
Q3:所得上限限度額を下回った時はどの手続きが必要ですか
A3:認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
【お問い合わせ】
中城村役場 こども課 子育て支援係
TEL:098-895-2271
令和4年度中城村子どもの居場所づくり運営事業に係る公募型プロポーザル実施について
提案参加事業者を募集します
令和4年度中城村子どもの居場所づくり運営事業に係る事業者選定については、公募型プロポーザルで実施しますので、提案参加事業者を募集します。
- 事業の内容
「令和4年度中城村子どもの居場所づくり運営事業業務委託仕様書」をご参照ください。
- 契約期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
- 応募審査スケジュール
実施内容 実施期日 1 公募開始 令和4年2月16(水曜日) 2 質疑受付期間 令和4年2月16日(水曜日)〜令和4年2月22日(火曜日) 3 質疑回答 令和4年2月24日(木曜日) 4 参加申込期限 令和4年2月25日(金曜日)午後5時 5 提案書等提出期限 令和4年2月28日(月曜日)午後5時 6 審査(プレゼンテーション) 令和4年3月3日(木曜日) 7 選定結果通知 令和4年3月上旬 8 協議 令和4年3月中旬 9 契約・運営開始 令和4年4月1日(金曜日)
- 参加要件、手続きの方法
「令和4年度中城村子どもの居場所づくり運営事業業務委託公募型プロポーザル実施要領」をご参照ください。
- 実施要領等関係資料の入手方法
募集要領及び提出書類などについては、次のファイルよりダウンロードしてください。
1.令和4年度中城村子どもの居場所づくり運営事業業務委託公募型プロポーザル実施要領(PDF)
2.令和4年度中城村子どもの居場所づくり運営事業業務委託仕様書(PDF)
3.参加申込書(様式第1号)
4.誓約書(様式第2号)
5.質疑書
【お問い合せ】
中城村役場 こども課 子育て支援係
TEL: 098-895-2271
令和4年度 沖縄県子育て総合支援モデル事業 【大学等進学促進事業】無料塾生徒募集案内について
沖縄県では、経済的に厳しい家庭の子供の大学等(専門学校含む)へ進学支援を目的とした「子育て総合支援モデル事業(大学等進学促進事業)」を行っており、今年度学校法人尚学院と琉大セミナーが県の委託を受け実施します。
平成26年度から始まりましたこの事業も今年度で9年目となり、これまでに、多くの生徒が進学の夢をかなえています。マスコミでも度々取り上げられる全国的にも注目度が高い事業です。つきましては、本事業の応募資格に該当し、希望される生徒並びに保護者に周知いたします。
支援対象者
大学(専門学校含む)への進学に意欲のある高校2・3年生の子どもで以下のいずれかに該当する者
- 児童扶養手当受給世帯の子ども
- 住民税非課税世帯の子ども(均等割り世帯は対象です)
- 児童養護施設等に入所している、または、里親に委託されている子ども等
- 生活保護世帯の子ども
募集期間
令和4年4月15日(金曜日)〜令和4年4月28日(木曜日) ※郵送の場合は当日必着
支援期間
令和4年5月9日(月曜日)〜令和5年3月31日(金曜日)
募集人数
300人
南部 那覇教室(80人) 那覇南部教室(25人) 与那原教室(25人) 糸満教室(30人)
中部 沖縄教室(60人) 宜野湾教室(25人) うるま教室(30人) 嘉手納教室(25人)
詳しくは下記の資料をご覧ください。
・子育て総合支援事業(大学等進学促進事業)無料塾生徒募集要項(本島中南部)
・子育て総合支援事業(大学等進学促進事業)学習支援内容(本島中南部)
【お問合せ】
学校法人尚学院 中部地区:コザ尚学院
TEL:098-930-6000
南部地区:那覇尚学院
TEL:098-867-3518
新型コロナウイルス感染症に関連するひとり親家庭支援について
1.子どもの預け先について
利用の際には、中城村役場こども課にて登録申請が必要です。
各事業の詳細については、こちら(PDF)をご参照ください。
(1)ひとり親家庭等日常生活支援事業
(2)ファミリーサポートセンター【全世帯対象】
2.経済的支援について
(1)母子父子寡婦福祉資金貸付
保育所や学校等の臨時休業、事業所の休業等により、保護者の就業環境が変化した場合等に「生活資金」貸付の活用が可能な場合があります。
※中城村役場こども課または中部福祉事務所(098-989-6603)まで電話相談ください。
(2)新型コロナに関連する特例貸付(生活福祉資金貸付)【全世帯対象】
問い合わせ:中城村社会福祉協議会098-895-6788 午前8時半〜午後5時(平日)
3.食料支援について
(1)フードバンク【ひとり親世帯に限らず生活困窮世帯対象】
在庫状況により対応できない場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ:中城村社会福祉協議会098-895-6788 午前8時半〜午後5時(平日)
【お問い合わせ】
中城村役場 こども課子育て支援係
TEL:098-895-2271
働く妊婦・事業者の皆様へ〜新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について〜
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、厚生労働省は、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
この措置は令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用されます。
具体的な内容については、リーフレットをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
・働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト「女性にやさしい職場づくりナビ」(外部リンク)
・職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(外部リンク)
こども医療費助成制度について
0歳から高校卒業程度までのお子様の医療費を助成しています。
年間事業、各種健診のお知らせ
親子健康手帳(母子健康手帳)
親子健康手帳(母子健康手帳)の交付手続き
妊娠したら、親子健康手帳(母子健康手帳)の交付手続きを行いましょう。
【交付申請を行う場所】中城村役場こども課
【交付申請に必要なもの】
※妊婦本人以外が代理で申請する場合は委任状が必要です。
妊婦健診が無料で受けられる受診票もお渡ししています。早めに親子健康手帳の交付申請をしてください。
中城村産婦健康診査事業
出産後2週間前後及び出産1カ月前後に各1回実施する産婦健康診査について、産婦1人につき、1回あたり上限5,000円の助成を行っています。
子育て世代包括支援センター
令和2年4月1日より、中城村子育て世代包括支援センターを設置しました。
中城村子育て世代包括支援センターでは、保健師、心理士、栄養士等の専門職がおり、子育てに関する様々な相談・訪問等の支援を実施しております。
保育・こども園係
(吉の浦こども園)苦情処理の公開
吉の浦こども園では、園に係る苦情への対応、苦情の円滑円満な解決を図るため第三者委員を設置しています。
社会福祉法第82条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えており、吉の浦こども園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めます。
苦情解決責任者
吉の浦認定こども園 園長 泉川 和代
苦情受付担当
吉の浦認定こども園 主任保育教諭 比嘉 祐理香
第三者委員会
1.儀間 好美
2.井上 京美
苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
a. 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
b. 第三者委員による解決案の調整、助言
c. 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)苦情処理についての報告
令和4年4月1日より令和5年3月31日の間に、苦情に対するお問い合せはありませんでした。
うえむら病院 病児保育事業の利用について
吉の浦こども園に遊びにきませんか
吉の浦保育所では、地域の皆様の交流の場として、毎週火曜日と水曜日の午前中に園庭を開放しております。
是非、吉の浦保育所へ遊びにいらしてください。
利用時間
毎週火曜日・水曜日 午前9:30分 〜 午前11:00 まで
※給食はございません。利用希望者は、前日の午前中までに吉の浦保育所へご連絡をお願いいたします。
利用定員
1日5組です。
その他
飲み物・着替え等のご準備をお願いいたします。
感染症対策の為、保育所へ入室前に手指消毒をお願いいたします。
また、体調がすぐれない場合は、利用を控えてくださいますようお願いいたします。
お問い合わせ先
中城村役場こども課
子育て支援係(1) TEL:098-895-2271
子育て支援係(2) TEL:098-895-2272
保育・こども園係 TEL:098-895-2134
FAX:098-895-3048
電子メールによるお問い合わせ