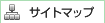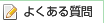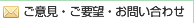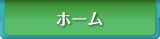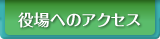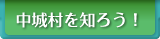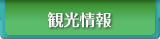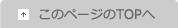保育関係補助事業
待機児童世帯助成事業
この要綱は、待機児童を有する保護者の経済的負担を軽減することにより、待機児童対策、及び安心して
子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的とした事業です。
・待機児童世帯助成事業のご案内
・補助金交付申請書
・補助金請求書
ひとり親家庭学童クラブ利用料助成事業
ひとり親家庭の学童クラブ利用料を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減と安心して子育てできる環境づくりに寄与することを目的とします。
対象者
村内に住所を有するひとり親家庭の保護者であって、学童クラブを利用している児童を監護している方。
助成内容
利用する学童クラブの利用料を、1人当たり月額5,000円を上限に助成します。
申請方法
≪提出書類≫
・児童扶養手当証書の写し等、ひとり親家庭であることがわかるもの
※状況に応じて、別途書類の提出をお願いする場合もございます。
≪提出先≫
・各学童クラブ
※中城村外の学童クラブを利用されている場合は、事前にこども課までご連絡ください
交付決定から助成までの流れ
上記の書類を利用する学童クラブへ提出していただいた後、内容を審査します。
決定が下りた方に対しては、直接学童利用料を減免します。
ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業
目的
ひとり親家庭における認可外保育施設の利用料の負担を軽減することにより、ひとり親家庭の生活の安定と自立促進に寄与することを目的とします。
対象者
中城村に住所を有し、次の4つの要件すべてに該当するひとり親家庭の母又は父になります。
(1)児童扶養手当又は母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者
(2)中城村に保育の必要性の認定を申請し、その認定を受けた子どもの保護者
(3)中城村に保育所利用の申し込みをしたが、定員に空きがない等の理由により認可外保育施設を利用している子どもの保護者
(4)0から2歳児の課税世帯
補助額
認可外保育施設の利用料(月額)― 認可保育園に入所した場合の保育料額(月額)
(補助の上限は33,000円です)
補助対象期間
申請をした日の属する月の翌月(当該日が月の初日である場合にあっては、当該日の属する月)から補助対象となりますので、お早めにお手続きください。
申請方法
中城村役場福祉課にて申請を行ってください。申請後、内容を審査し、利用資格者書もしくは却下通知を送付致します。
≪申請時に必要なもの≫
(1)児童扶養手当証書の写し、又は、中城村母子及び父子家庭等医療費受給者証の写し
(2)支給認定書(市町村が発行)
(3)ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用証明証(認可外保育施設記入)
(4)認可外保育施設の利用料月額とその内訳がわかる資料(契約書、しおり等)
(5)印鑑(認印可)
変更及び喪失の届出
・中城村外へ転出する際や上記「対象者」の要件に該当しなくなった時は、福祉課まで届出をしてください。
注意事項
・次年度も本事業での補助を希望される場合、年度内での再申請が必要となります。
病児保育事業
病児保育事業とは
保育所に入所中の児童等が病中で回復期には至っていないことから、集団保育が困難な期間、一時的にその児童を預かることにより、保護者の子育てを就労の両立を支援することを目的としています。中城村では下記の施設で実施しています。
実施施設
・医療法人海秀会 うえむら病院
・医療法人ひまわりの会 太田小児科医院
利用料金
・保育料2,000円
・食費500円
※以下のいずれかに該当する場合は、保育料の免除が受けられます。
(1)生活保護世帯は、保育料全額無料
(2)市町村民税非課税世帯は、保育料一部免除(1,000円)
利用方法
1.病児保育を利用する前日までに、役場で病児保育利用登録申請書を記入し登録を行う。
(登録時には印鑑が必要になります。印鑑以外に書類等は必要ありません。)
2.利用時は病院に備えつけている、病児保育利用申込書を記入し病院へ提出。
3.医師による診察を受けた後、利用可能と判断した場合、利用開始となります。
※定員に達している時、症状等によりご利用できない場合がございます。
第3子以降保育料無料化事業
第3子以降保育料無料化事業とは
第3子以降の児童の保育所等への入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的とした事業です。
第3子以降の児童とは
小学校就学前児童が3人以上いる世帯のうち当該世帯の3人目以降の児童のことをいいます。下の例1の場合、一番上の子が小学校に就学しているため、4歳児から数えることになり、0歳児は2番目となるため、該当者なしとなります。例2の場合は、0歳児が3人目に該当します。例3では、4歳児が第3子、0歳児が第4子となりどちらも該当児童となります。
- 例1、家族構成が両親と子ども3人(小学校1年生、4歳児、0歳児)
- 例2、家族構成が両親と子ども3人(幼稚園生、4歳児、0歳児)
- 例3、家族構成が両親と子ども4人(幼稚園生、5歳児、4歳児、0歳児)
対象児童
この事業の対象となる児童は、中城村内に住所を有し、認可外保育施設に入園、入所している第3子以降の児童とする。また、認可外保育施設に関しては、児童福祉法第59条の2に基づき、県知事へ届出をしている施設であれば村内外を問いません。
保育料補助内容
補助対象となる保育料は、公立保育所においては保育料徴収基準額表における基準額の全額、認可外保育施設においては認可外保育施設長と保護者との契約により保護者が支払うこととされている保育園における保育に準じる基本的な保育サービスの利用に要する費用となっています。教材費、入園料などは補助対象外です。
交付金決定までの流れ
交付申請書を中城村役場窓口(こども課)にて受取り、記入の上、認可外保育施設との契約書(保育料の判別できるもの)の写しを添えて提出してください。 その後、内容を審査し、決定通知書若しくは却下通知書を送付いたします。
交付方法
補助金請求書に毎月、若しくは複数月分の領収書を添付して請求して下さい。保護者名義の口座へ振込いたします。支払時期は、請求書提出月の翌月中旬頃となります。
第3子以降保育料無料化事業様式
お問い合わせ先
- 中城村役場こども課
- 電話 098-895-2134 内線186
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ