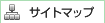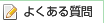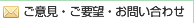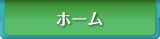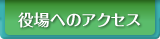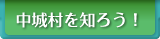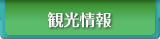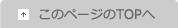国民健康保険
- 国民健康保険の目的やしくみ
- 国民健康保険に加入するのはこんな人
- 国民健康保険への届出は14日以内に
- 国民健康保険に加入するとき
- 国民健康保険をやめるとき
- その他の場合の手続
- 70歳になったら
- 現行の健康保険証は令和6年12月2日より、発行されなくなります。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
- 中城村国民健康保険加入者のマイナ保険証の利用登録「解除」について
- 中城村国民健康保険加入者の資格確認書交付申請について(要配慮者等)
- お問い合わせ先
国民健康保険の目的やしくみ
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金(国保税)を出し合い、安心してお医者さんにかかれるように、お互いに助け合おうという制度です。
国民健康保険に加入するのはこんな人
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が、国民健康保険に加入します。
- お店などの経営している自営業の人
- 農業や魚業を営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
国民健康保険への届出は14日以内に
届け出が遅れると次のような不利益を被ることがあります。
加入の届け出が遅れると
- 保険税は届け出をした日からではなく、資格を得た月まで遡って払う事になり、一時的に支払いの負担が大きくなる可能性があります。(遡及賦課)
- 保険証(資格確認書・マイナ保険証)が無い間の医療費は、原則全額自己負担となります。
やめる届け出が遅れると
- 資格を喪失した保険証で診療を受けると、国保が負担した診療費を後で返すことになります。
- 他の健康保険に加入している場合、保険税を二重払いすることになります。
国民健康保険に加入するとき
| どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転出により他の市区町村から国保を喪失して転入したとき |
・他の市区町村の転出証明書 (持っている方のみ・転入者全員分) (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
|||||
| 職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者から外れたとき) |
・健康保険資格喪失証明書 (持っている方のみ・加入者全員分) (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
|||||
| 子どもが生まれたとき |
・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
|||||
| 生活保護を受けなくなったとき |
・保護廃止決定通知書、マイナンバーカード (持っている方のみ) (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
|||||
※同じ世帯員以外の方が保険証を受取る場合は委任状が必要になります。
国民健康保険をやめるとき
| どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他の市区町村へ転出するとき |
・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
|||||
| 職場の健康保険に加入したとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき) |
・国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 (持っている方・全員分) (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
|||||
| 国保の被保険者が死亡したとき |
・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
|||||
| 生活保護を受けるようになったとき |
・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 (持っている方のみ) (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
|||||
その他の場合の手続
| どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったとき |
・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 (持っている方のみ・変更のある全員分) (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
|||||
| 修学のため、別に住所を定めるとき |
・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 (持っている方のみ) (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
|||||
| 資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき |
・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等) (ある場合) |
|||||
※同じ世帯員以外の方が保険証を受取る場合は委任状が必要になります。
70歳になったら
70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
現行の健康保険証は令和6年12月2日より、発行されなくなります。
令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
※有効期限(令和7年12月1日)まではお手持ちの被保険者証で医療機関等の受診ができます。
〇マイナ保険証をお持ちでない方(保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方)
有効期限までは、お持ちの被保険者証で医療機関等の受診が可能です。
(転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。)
令和6年12月2日以降、新規加入の方や紛失した方などでマイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付され、これまでどおり一定の窓口負担で医療機関等の受診が可能です。
〇マイナ保険証をお持ちの方(保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有している方)
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を簡易に把握いただくため、新規加入時や負担割合変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
オンライン資格確認が導入されてない医療機関や、何らかの事情でマイナ保険証が使えない場合などに「資格情報のおしらせ」と「マイナ保険証」を併せて提示することで医療機関等を受診することができます。
・保険税を滞納した場合の保険証について
これまでは短期被保険証を交付していましたが、令和6年12月1日以降は発行いたしません。
納付の相談がなく、国民健康保険税を滞納している世帯については、医療機関等の窓口で医療費をいったん全額お支払いいただく場合もありますので、国民健康保険税の期限内納付が困難な場合はお早目にご相談ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
マイナンバーカードを保険証として利用するための準備は2ステップ
ステップ1 マイナンバーカードを取得
申請方法は選択可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2 マイナポータルから初回登録(ひも付け)
利用登録の方法
・マイナポータルから行う マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイトへリンク)
・セブン銀行ATMから行う (セブン銀行ATM)
・医療機関・薬局の受付で行う
お手伝いが必要な方は中城村役場健康保険課課窓口でも登録可能です。
登録時はマイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を入力します。
マイナ保険証を使うことでいくつかのメリットがありますので、ぜひご利用ください!
1、 データに基づく適切な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
2、 転職や転居等による保険証の切替や更新が不要
今後、転職や転居などで必要だった保険証の切替や更新が不要になります。
※なお、保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)は、従来通り、保険者への異動届等の手続きは必要です。
3、 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※オンライン資格確認が導入されていない医療機関等では、引き続き健康保険証の提示が必要です。
医療機関によって、オンライン資格確認の導入時期は異なります。
利用できる医療機関については、厚生労働省のホームページで確認できます。
(または、医療機関へ確認お願いします。)
※令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
また有効期限までは、お持ちの被保険者証で医療機関等の受診が可能です。
関連リンク:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
中城村国民健康保険加入者のマイナ保険証の利用登録「解除」について(健康保険課での受付は令和6年11月1日より開始します。)
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方が、「マイナ保険証」の使用をやめて、「資格確認書」(令和6年12月1日までは健康保険証)の使用を希望する場合は、登録解除の手続きが必要となります。
加入している健康保険の保険者へ申請することで、登録解除することができます。
【申請できる方】中城村国民健康保険加入のマイナ保険証をお持ちの方
【申請場所】中城村役場 1階 健康保険課
【必要なもの】
〇本人の場合:顔写真付きの身分証
※本人が未成年の場合は親権者の申請により解除可能。
親権者の身分証を持参のうえ、親権者の来庁をお願いします。
〇代理人の場合:代理人の顔写真付きの身分証
(本人以外) 委任者(本人)の顔写真付きの身分証の写し
本人記入の解除申請書(代理人の記載まであるもの)
・申請書:マイナ保険証利用登録の解除申請書
※ 申請方法は加入している健康保険の保険者へご確認お願いします。
※ 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
※ 利用登録の解除を申請した方には、保険者から資格確認書を交付します。解除後、医療機関等を受診される際には資格確認書の持参が必要です。
※ 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1〜2か月程度時間がかかる場合があります。
※ 同一世帯の方(世帯主を含む)が、同一世帯のほかの方の利用登録解除の申請をする場合も代理人の場合と同じになります。
中城村国民健康保険加入者の資格確認書交付申請について(要配慮者等)
マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診が困難な方(要配慮者等)は、申請することで「資格確認書」を発行できます。(更新時の申請は不要)
※ マイナ保険証の本人確認は顔認証でも可能です。
※ マイナ保険証を今後も利用するつもりがない場合は、マイナ保険証の利用登録解除申請してください。
申請できる対象者
・ 要介護要支援認定、障がい認定を受けている方
・ マイナンバーカードを紛失した方
・ その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方
※ 念のため資格確認書を持ちたいという理由の申請は対象外になります。
※ マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する人は対象外になります。
※ 介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がない高齢者は対象外になります。
申請に必要なもの
・窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・要介護要支援認定、障がい認定を受けている方は介護保険被保険者証、身体・精神障がい者手帳、療育手帳
代理人による申請に必要なもの
・窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・要介護要支援認定、障がい認定を受けている方の介護保険被保険者証、身体・精神障がい者手帳、療育手帳等
・委任状
申請場所
中城村役場 1階 健康保険課